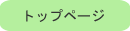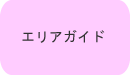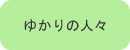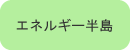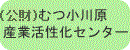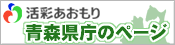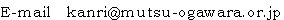むつ小川原ガイドのページです

元祖津軽三味線の名人

苦しみを越えた温もり
昭和48年12月、東京渋谷の小劇場ジャン・ジャンに初めて出演し、以来、平成7年3月の最後の公演まで、20年にわたる定期公演は続けられた。
その初めての演奏会の合間に、三味線と竹山の閑係が、やわらかで訥々した語り口で自己紹介のように語られた。
「あたしたちゃ 十四歳の時に 三味線というものを 習いました。あたしは この三味線というものを 好きで 習ったものではありません。
三味線を弾くということは つらいものでありました。今では皆民謡民謡と 民謡をきいてくれて 三味線というものを立派にみんなみてくれるようになりまして ありがたいなあと あたしは 思います。
どうしてどうして 大変なくるしいものでありました。日に三度のご飯も あんずましゅう食べられにゃあ時代もありました。」
太棹三味線というと、先ず浄瑠璃のペンベーンという重厚な音色に、思わずうなりたくなるあの独特な演奏を思い出す人も多いだろう。撥をはじき回すように、打つ、掬う、分裂音をつくるといった高度なテクニックを駆使しながら、軽やかで華やかな津軽三味線の演奏法が確立したのが明治の末頃という。
大正時代に入り民謡興業が全国的に盛んになると、三味線奏法も飛躍的に進歩する。マイクのない時代、観衆にアピールするために、叩きつけるような激しい奏法をもって、高橋竹山や竹山生涯のライバルといわれた木田林松栄らの名手が登場したのである。
津軽三味線との出会い
高橋竹山。本名定蔵。明治43年(1910)平内村小湊の生まれ。幼児の時に麻疹が原因で半ば失明。大正2年(1913)に東北地方を襲った大凶作は、米二分作という悲惨な状況で、「草根木皮を食として辛うじて露命をつないだ」と記録が残されている。医者にかかることなど思いもよらない話だった
親は日の不自由なわが子の行く末を案じ、十四歳の時に戸田重次郎に弟子入りさせた。定蔵はそこで門付けの方法と三味線を学んだ。
津軽三味線は、明治の初めに津軽地方一帯にあった「坊さま三味線」が始まりとされる。坊さま(盲目の人)が人家の前で三味線を弾きお金や米を恵んでもらって歩き、暮らしを立てるのが門付けである。どの家でも門付けには、何がしかのものを恵むという社会的な習慣があった。
流浪の一人旅は、県内はもとより、北海道・樺太にも及んだ。しかし門付けでは、たくさん回ろうという気持ちが勝り、三味線を上達しようという気持ちは沸かなかったと、後に竹山は言っている。一時は三味線を捨て、マッサージ師になろうとしたこともある。
しかし、竹山は津軽民謡一座や浪曲の三味線伴奏を務めるうちに、他の人の芸に接することで自分の三味線に対する熱い思いに気づいた。ー「三味線上手になりたい」。
津軽民謡の名手といわれた成田雲竹との出会いが、竹山の三味線の修練に磨きをかけた。三味線がついていなかった古い津軽民謡に、新しい音楽性を目指していた雲竹が伴奏を付けるよう依頼したのである。
以来、二人は師弟コンビを組み「十三の砂山」「鯵ヶ沢甚句」「弥三郎節」等の津軽民謡をアレンジして世に送り、全国に歌い広めることになる。民謡界に大きな変革をもたらした二人の功績は極めて大きかった。竹山にとっても、大きな飛躍のきっかけになった。
死ぬまで舞台に
津軽三味線奏者として成功を収めたのは、その卓越した演奏技術を駆使し、自ら作曲した「岩木」の真価を知られてからのことである。竹山のめくるめく繊細華麗な旋律は、太棹三味線の可能性を極めたものといえるだろう。そこには、世界中の弦楽器を研究し、津軽三味線に応用した探求心と、三味線に対する深い思いがあったことはいうまでもない。
昭和47年青森放送局制作の「寒發」がテレビ部門で芸術祭優秀賞を獲得する頃には、竹山の名声は確固たるのものになった。
平成10年2月5日、長く患った喉頭ガンで逝去。87歳。その前年の暮れまで地元では演奏会をしていたという。
「死ぬまで舞台に上がらなければマイネ」の言葉通りに。