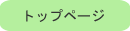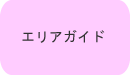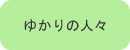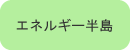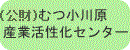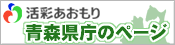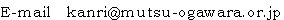むつ小川原ガイドのページです

ダンディズムにこだわったアウトロー監督

映画好きのオタク少年
川島雄三は、大正7(1918)年下北郡田名部町(現むつ市)に、商家の三男として生まれた。身体虚弱、運動はダメだけれど、勉強は優秀で読書が好きという、今でいう「オタク」に見えたかもしれない少年だった。
知識欲旺盛な子供に見られる早熟ぶりは、野辺地中学生の時すでに「純然たる日本文学といえるのは近松や西鶴のような庶民文学、俳句、川柳だ」と主張したという逸話からもよくわかる。そうした中でも一番の関心は映画にあったようだ。学校の巡回映画では飽きたらず、禁止されていた町の映画館にも通っていたという。
昭和10年、明治大学専門部文芸学科へ進学すると早速映画研究会に入り、飛鳥田一雄、時実象平らと知り合う。映画の理論的研究、映画監督を招いた勉強会、同人誌での作品論評など、映画に浸り続けた学生生活を送る。卒業して松竹大船撮影所の助監督試験に合格する。
アウトロー監督の誕生
大船撮影所のほとんどの監督について仕事をするのだが、才能とその個性的な性格ゆえに、どの組にも安住できない苦しい助監督時代を送る。
昭和18年、日本国民にとっては苦難の始まりの年だったが、川島にとってはそれが幸いした。徴兵されていく監督陣の穴埋めに行われた監督昇進試験に、首席で合格。昭和19年、織田作之助原作の「還ってきた男」で監督デビューを果たす。このシナリオは織田作之助が書いた最初で最後のシナリオであったが、映画は大政翼賛会の世に興行的には不評だったため、助監督に降格してしまう。
川島は、20年間の監督生活で51本の作品を残し、駄作、凡作、傑作、秀作とその評に安定したものがない。むしろ、本人が安定を拒んだかのような風もある。
しかし才能は、どの作品にもこぼれ出ている。新しいスターの芽が出始めていた石原裕次郎を起用した時代劇「幕末太陽傳」は、その真骨頂だった。フランキー堺という個性も発掘した。さらに、原作者水上勉でさえも映画化は無理といった「雁の寺」の成功で、純文芸映画の境地も開いた。
「幕末太陽傳」で俳優として発掘されたフランキー堺と川島は、次は「写楽」と決めていたというが、川島は、昭和38年それを待たずして急逝した。30年後、残ったフランキー堺は、自ら写楽を発掘した出版元蔦重を演じ、平成7年篠田正浩の監督で映画化した。川島とともに抱いた構想を実現したのである。
何故、次は「写楽」だったのか。江戸時代後期の浮世絵師、東州斎写楽は謎の人物。生没年不詳、本名も不詳。大胆なデフォルメを利かせた個性的な役者似顔絵は、当世の不評にもかかわらず、ライバルの歌川豊国あるいは喜多川歌麿らに大きな影響を与えたのである。写楽の異能ぶりは、その後も欧米人の高い評価を受けて、大正以降日本でも関心を集めることになった。
「貸間あり」「幕末太陽伝」「天使も夢見る」「しとやかな獣」「女は二度生まれる」「イチかバチか」、川島の映画表現は一般的に「異能」と評されるが、さらに誰もなしえない表現の境地を、謎の浮世絵師・写楽に求めていたのかも知れない。
下北が育んだ純粋な心
小津安二郎、黒沢明、今井正、溝口健二、今村昌平、木下恵介、日本映画の輝きが増してきた時代に、無視できない存在として次に何が出てくるかを期待させた川島は、松竹に始まって、日活、東京映画、大映とその籍を変えていく。
「いい作品を作るというより、才能があるんだからいつでもできると思っていたのではないか」という見方もあるが、しかし、それはむしろ日々進行していく病魔と闘いながら、死の悲壮感や絶望からも自由になって映画を作りたいという欲求、完成させ円満に成就するのでなく、映画作りに己の才能を解き放ちたいとする純粋な欲求ではなかったか。
後まで下北の出身であること、その家族や生い立ちについて、何も語らなかったのも彼一流のダンディズムであろう。
生き急いだかのような45歳の生涯。その純粋一徹は、下北以外の何ものでもない。むつ市に追悼の石碑があり、毎年のように記念の映画会が開かれている。