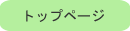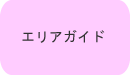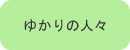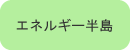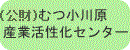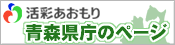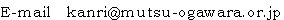むつ小川原ガイドのページです

飛行機づくりに翔んだ男
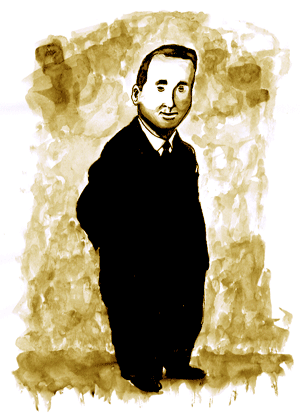
技術の目
明治30年代の頃。大湊村のわんぱく少年達は、海に丸木船を浮かべては遊んでいた。しかし、どうもバランスが悪くてひっくり返ってしまう。丸木は見た目と違い均質ではないからだ。
その時、「先に丸太を浮かべて、安定したところで喫水線を決めれば大丈夫」と仲間にアドバイスした少年がいた。後にわが国航空機技術の第一人者となる工藤富治である。父も祖父も船大工だった工藤には、物づくりの家庭環境の中で確かな技術の目が養われていた。
工藤富治は、明治22年(1889)下北郡大湊に生まれ、昭和34年(1959)大湊に没する。70年にわたる生涯は、必ずしも陽の当たる栄光の道ではないが、単身海外に乗り込んで先端技術を体得し、日本の航空機製作の発展に先導的な役割を果たしたことは間違いない。
航空機製作への情熱
初めてライト兄弟が飛行機で飛んだのが、明治36(1903)年。欧米諸国の航空機の進歩に著しく後れていた日本は、先進諸国の機材を輸入して研究したり、ライセンス生産を行うなどの努力をして遅れを取り戻そうとしていた。
工藤は小学校高等科を卒業してまもなく、大湊の海軍水雷団の修理工場に見習工として就職した。ここで工藤は機会工としての腕を磨いた。
大正5年(1916)、ロシアで飛行機製作技術者を募集していることを知り、単身ロシアへ。ヨーロッパでは、第一次世界大戦がまだ終結していない不穏な情勢下にあったにもかかわらず、妻子を残してでも工藤をロシアに駆り立てるものがあった。
ドボワティーヌとの出会い
シベリア鉄道でユーラシア大陸を横断し、黒海に面した都市オデッサへやって来た工藤は、そこで生涯最良の友となるフランス人ドボワティーヌと出会う。後に、工藤はフランスに渡り、ドボワティーヌの起こした会社で共に飛行機づくりに取り組むことになる。
手始めはD1という、当時としては画期的な全金属製の飛行機だった。この飛行機は日本でも1機輸入されており、大正13年(1924)に実際に見た当時の学生木村秀政博士はその著書にこう記している。「ドボアチンによって設計されたD1C1型戦闘機が際だって洗練された機体で注目を引いた。・・・全部ジュラルミンの薄板ででできておりピカピカ輝いていた」
最新鋭機でさえも、木製の骨組みに羽布を張ったものが普通の頃。まさにまぶしいまでに輝く飛行機であった。
この飛行機に関するフランスの文献には「メカニシャン・クドー」の名が記されている。
トレ・デュニオン号
その後昭和6年(1931)、工藤が心血を注いだD33型「トレ・デュニオン号」が、世界的名パイロットのルブリとドレーにより周回飛行で長距離世界記録を樹立する。折しも時代は、リンドバーグの大西洋横断飛行の成功を契機に、太平洋横断と世界早回り飛行の大飛行時代の最中にあった。
「トレ・デュニオン号」もパリ〜東京無着陸飛行に挑戦する。「トレ・デュニオン号」が東京に着いたときに工藤が整備をして、そのまま一気に太平洋を横断しようという計画だった。しかしこの計画は、バイカル湖手前に不時着、2回目もまたウラル山中に墜落してルブリが死亡するという悲劇で終わった。
国産機「航研機」の世界記録
昭和7年(1932)帰国した工藤は、浜松飛行機製作所を経て、東京瓦斯電気工業で日本での飛行機製作に携わる。
昭和10年(1935)東京帝大航空研究所が、基礎技術の研究成果を総合して長距離機「航研機」の試作を行うため、製作会社を探していた。
そこでメカニシャン・クドーの存在、しかも彼がかつて製作したD33型と同じ方式という有力な実績を生かして、東京瓦斯電の工藤を工場長に製作が開始された。製作の過程は多くの困難と試行錯誤の連続であったに違いない。工藤は病気を患い、九分通り完成した段階でやむなく仕事を離れた。この「航研機」が達成した、昭和13年5月の周回航続距離1万1651kmは、現在もなお国際航空連盟公認の世界記録を樹立した唯一の国産機である
大湊に帰郷した工藤は、国際的な経験を元にしてわが国の航空力整備にむけた意見を草案ながらまとめたりもしている。
終戦後は、ついに飛行機作りの現場に戻ることはなかった。孫達に与えた手づくりの飛行機が不思議なほどよく飛んだという。飛行機づくりへの限りない情熱か、あるいは燃やし続けられなかった無念の思いか。今は知る由もない。