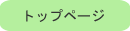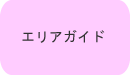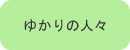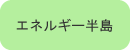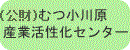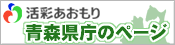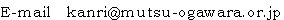むつ小川原ガイドのページです

国際社会への道を開拓した東北人

旧五千円札の肖像でおなじみとなった新渡戸稲造だが、その人となりは意外と知られていない。
稲造は、文久2年(1862)新渡戸十次郎の三男として生まれた。三本木原開拓の祖・傳は祖父にあたる。
9歳の時上京し、築地外人英学校に通い始める。明治10年(1877)15歳で開拓使札幌農学校に入学、キリスト教に接する。後に哲学者となる内村鑑三は同級生で、この時共に洗礼を受けている。
東京帝大での試問で、「太平洋の橋になりたい」と答えた決意は、翌年米国へ私費留学することで具体化の一歩を踏み出した。
彼の地でクエーカー教徒(キリスト教の一派)となり、「クエーカー主義においてはじめて、キリスト教と東洋思想とを調和させることができた」と述懐している。
ドイツ留学後は札幌農学校教授となるが、病気療養のため辞職する。
静養先の米国西海岸(メアリー夫人の故郷)で「武士道」を執筆、翌年「Bushido,The Soul of,Japan」が米国で出版される。この本は、後年ルーズベルト大統領の愛読書としても有名になった。
大正8年(1919)、国際連盟事務局次長に就任。ユネスコの前身となる国際知的協力委員会の設立に際しては、ベルグソン、キューリー夫人、アインシュタインら世界的学者の結集に奔走した。
文字通りの国際派であった新渡戸稲造は、日本国内の状況に対しても、国際的な視野から客観的かつ的確な見方をしている。
北海道・東北を旅行した最後の機会に、西日本や南日本の恵まれた気候とは明確に違うことを指摘。「北国の人は愛想良く温和な性質や、市民生活の楽しみ方は欠けているとしても、性格の不屈と独立においては、南国の兄弟にまさる」と。
稲造自身もまた、祖父伝来の血を受け継ぎ、国際社会という当時の日本にとってはまさに未開の地を開拓した一人であった。
果敢で孤立を厭わない不屈の精神は、まさに東北人そのものであった。